同条は、民法第958条の2第1項の規定により与えられた特別縁故者への財産分与及び民法第1050条第1項の規定により確定した特別寄与者への特別寄与料が相続財産から与えられた場合は、被相続人から遺贈により取得したものとみなす「みなし遺贈」の規定である。
1.特別縁故者及び特別寄与者の費用負担について
まず、このケースで問題になりがちな、特別縁故者及び特別寄与者の費用負担の控除可能性について以下に検討する。
論点1:特別縁故者及び特別寄与者が負担した被相続人に関する生前の費用の控除について
特別縁故者又は特別寄与者が現実に負担した被相続人の葬式費用、療養看護に関する入院等費用は、債務控除可能であるか。
この点につき相続税法基本通達4-3において、相続開始時にまだ支払われていないことを条件に、実務上当該費用の控除を認めている。
したがって、これらの費用を控除した価格をもって、当該分与価格あるいは特別寄与料として申告することになる。
論点2:特別縁故者あるいは特別寄与者が、相続財産の分与の申立に関する手数料や費用について負担した場合の控除について
特別縁故者あるいは特別寄与者が、相続財産の分与の申し立てを家庭裁判所にした際に要した手数料、郵送料あるいは弁護士費用等の諸費用を分与財産の価格から差し引くことはできるか。
この点について最高裁昭和63年12月1日判決(の下級審である大阪高裁昭和59年7月6日判決)によると、諸費用を控除することはできないとした。
理由としては、当該債務控除の規定は、相続人と包括受遺者にのみ適用されるものであり特別縁故者は控除債務に該当しないこと、必要経費控除の観念は資産税制下においてなじまないこと、これらをもって費用の控除可能性を否定した。
したがって、家庭裁判所への申し立てに要した費用を控除することはできないと解される。
2.相続開始時によるべきか、審判確定時によるべきか
次に、適用すべき法律の施行時期の争いについて考えていきたい。
論点3:適用すべき相続税法は、相続開始時施行の法か審判確定時施行の法か
これについては先に挙げた判例(最高裁昭和63年12月1日判決)においてまさに争われ、結局「審判確定時の相続税法を適用せよ」と主張していた納税者側が敗訴し、「相続開始時の相続税法を適用せよ」と主張していた課税庁側が勝訴している。
すなわち、特別縁故者による家庭裁判所による審判の申立により、相続開始から審判確定までの間に時差が生じた場合、適用すべき相続税法は審判確定時の法ではなく、相続開始時の法であるということである。
論点4:財産評価すべき時期は、相続開始時か審判確定時か
では、特別縁故者において、相続税の財産評価の時期も、相続開始時となるのか。
これについては直接的に争われた先例を承知していないが、先述の判例においては「財産分与により取得した財産の価格評価が審判の確定時を基準に行われている」ことを前提としており、訴訟当事者どちらも問題視することなく、また、裁判所が直接的にこの点について追及することもなく、判決が確定している。
先ほどの論点3においても述べたように、財産分与による財産の課税時期が相続開始時であり、その課税につき相続開始時の相続税法が適用されるのならば、財産評価も相続開始時によるのではないか、とも考えてしまう。
正直なところ、筆者としては疑問が残るが、今日の実務においてはもっぱら「審判の確定時の評価額」をもって相続税の計算がなされている。
なお、相続税法第4条を文理解釈すれば済むのではないか、という指摘はこの場合あたらない。
たしかに、同条において「その与えられた時における当該財産の時価に相当する金額を……遺贈により取得したものとみなす。」と定められており、「与えられた時は家庭裁判所による審判の決定がなされた時なのだから、審判確定時に財産評価をするものと解するのが相当ではないか」と云位したくなる気持ちもわかる。
しかし、先の判例において、その論は否定されている。
曰く、税法は民法などの私法の規定とは異なる条理であるのだから、同一の意味内容と解すべきではなく、その取得時期について、民法上の特別縁故者の条文と同一に解しなければならないものではないというのだ(筆者意訳)。
つまり、特別縁故が決まったのは審判の確定時でも、その財産が与えられたのは相続の開始時であると、擬制することができる(すなわち、そのようにみなすことができる)ということである。
だからこそ、この裁判において、特別縁故者の審判に時間を要し、タイムラグが生じた場合であっても、相続開始時の(基礎控除額が定められた)相続税法が適用されるという結論に至ったのである。
ならば、相続開始時の相続税法が適用されるというのであれば、当然、財産評価についても相続開始時の相続税法の規定に基づき評価すべきと考えてしまうのだが、これは余計な一考なのだろうか。
あなたは、どう思うだろうか。
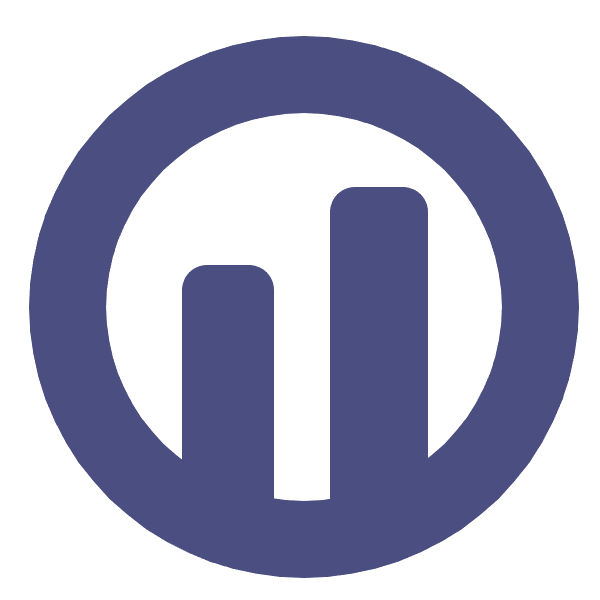 THE BUSINESS
THE BUSINESS