みなし贈与規定の立法趣旨
贈与税についても定められている相続税法においては、以下のとおり各条文において、みなし贈与の規定が設けられている。
- 保険金(相続税法第5条)
- 定期金(相続税法第6条)
- 低額譲受(相続税法第7条)
- 債務免除等による利益(相続税法第8条)
- その他の利益(相続税法第9条)
- 信託に関する権利(相続税法第9条の2)
本来、贈与は、「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法第594条)のであるから、一方的な意思表示や無償でない処分行為については民法上、贈与とならない。※1
しかし、税の公平負担の観点から、相続税法においては「みなし贈与」の規定を設け、税負担の取りこぼしがないように定められている。
論点:どの程度から「著しく低い価格の対価」となるか
相続税法第7条においては、低額での譲渡の場合も「みなし贈与」として課税対象になりうることを示している。
ここで実務上問題になるのが、何をもって同条にいう「著しく低い価格の対価」となるかだ。
一応の基準については、所得税法や法人税法において、『時価の2分の1に満たない金額をいう』ものとされている。※2
ところが、相続税法には同様の規定が存在しない。
ここで、これらの隣接している税法の規定から類推して適用しようとする傾向がある。
しかし、裁判例において、著しく低い価格の対価は、必ずしも時価の2分の1に満たない金額とは限定していない。※3
そのため、総合的に実状を勘案し、社会通念に従って判断するという、苦しい実務上の運用となっている。
このような事情があるため、私個人は、課税関係が複雑になる「みなし贈与」に類する法形式を採用するのではなく、単純な金銭の贈与を取り入れるなどした「税額の算出が予測可能性において高い取引形態」を模索するのも一考ではないかと思う。
この点については、税理士や当事者同士が良く話し合い、様々な方法による財産の移転手段を検討することが、今すぐにできる最善の策と思われる。
【注釈】
※1 狭義厳格に解釈すれば、片務契約及び無償契約の側面を強調することとなる
※2 所得税法第36条・40条・59条第1項第2号、所得税法施行令第169条、法人税法22条・22条の2・37条
※3 大阪高判平20.3.12税資258号順号10916、東京地判平19.8.23税資257号順号10763など
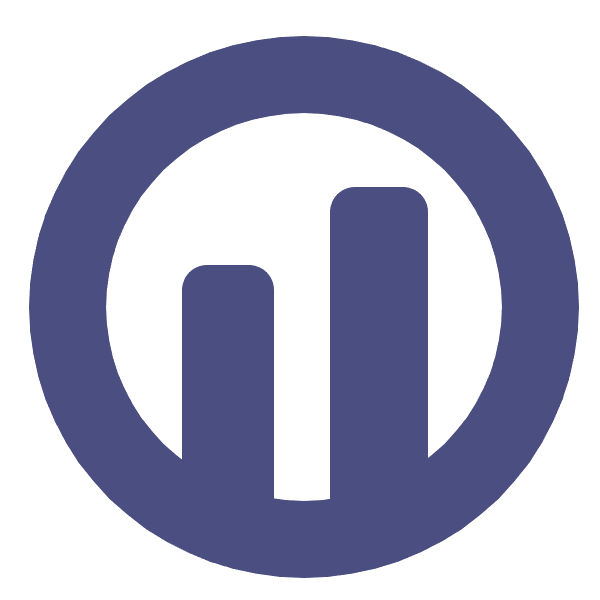 THE BUSINESS
THE BUSINESS