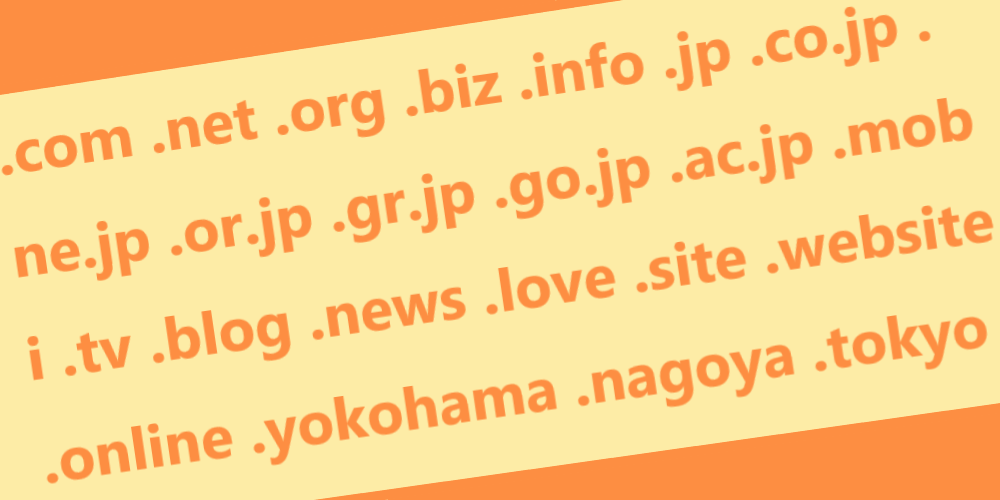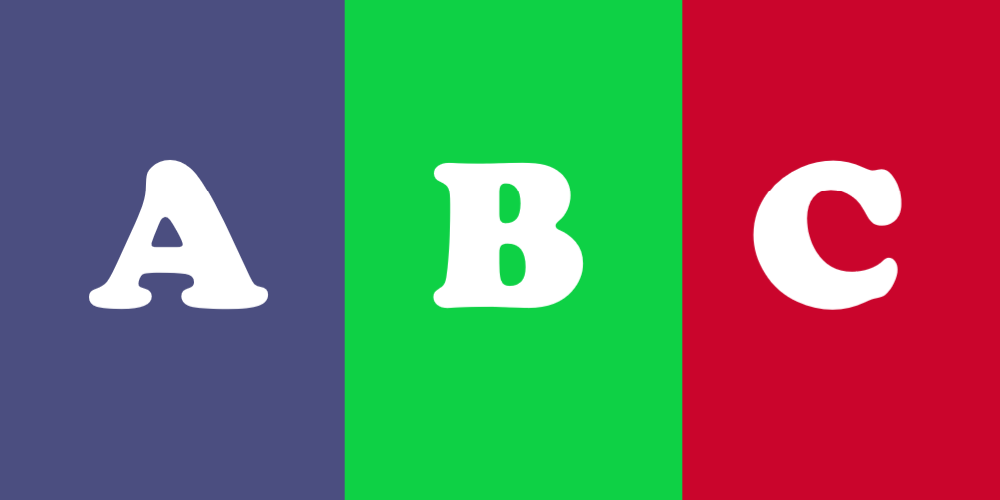今日は、高野登さんの著書『リッツ・カールトン「型」から入る仕事術』(中央公論新社、2014年)より、「仕事の型」の習得法と展開法を読み解いていきます。
仕事の型の習得法
皆さんが働く世界では、仕事の型のようなものがあると思います。
新人は、この仕事の型を身につけるところからスタートするはずです。
その際、高野さんはこんな心持ちが大切だと説きます。
1.日々を新たに送るための意識という型
あなたは、朝目覚めたら、どんな想いで起き上がるでしょうか。
「そもそも、何にも考えていない」
「今日も仕事かぁ…と、ぐったりしている」
色々な想い(というより意識?)があると思いますが、著者はこう言います。
朝目覚めたときに、今日も新しい一日がスタートできるということに感謝できているかどうかが初めのステップだと思います。
と、いうのも、日本人は一日を大切に過ごす祈りの型を身につけていたと。
朝起きて布団を畳み、家の中や周りを掃除し、次にお茶を入れてご飯を炊いて、一杯目を仏様にあげていた、と。
「今日一日、見守っていてください」という想いを伝えることを習慣にしていた、と。
だけれども現代では、そのような習慣は廃れていき、感謝をする習慣が無くなってきているのではないか。
そのような問題提起をしています。
たしかに私自身、そういった前向きな気持ちになっていなかったように思えます。
そのような感謝の習慣を職業に持ち込むと、働く気持ちも変わることでしょう。
2.社長になった人とそうでない人の逸話
著者は次のようなケースがあったと言います。
あるアメリカの鉄道会社で、列車の枕木を修理する仕事を熱心な気持ちで働き、その後社長になった人がいました。
その社長が昔の同僚から「お前は時給2ドルのために働いていた」と言われた時、「俺は当時から、この鉄道を使ってくれる人たちの安全と幸せを考えながら仕事をしていたんだ」と返しました。
社長の昔の同僚は、今も時給を稼ぐために働いています。
しかし、この社長は、「安全で快適な旅を、列車に乗ってくださるお客様のために提供すること」に意識をフォーカスさせていたというのです。
たしかに、両者には仕事をする上での意識の差ないし感謝の差がありました。
いやいや、こんなの精神論じゃないか。
そう思う気持ちも分かります。
しかし、働き方は会社ではなく社員自身が決められるというのは、事実です。
給料と同等の働き方でいいやと考えるのか、一歩進んでその先を見るのか。
あなたはどう思うでしょうか。
私は、肯定的です。
自分自身の精神衛生にも良いですし、見ている人は見ていますからキャリアアップにも間接的に繋がるのではないでしょうか。
決して、損ではないと思います。
例え社長になれなかったとしても、私はこの働き方を支持したいと思います。
3.日常の職場で出来る型
では、日常の職場では、具体的にどのような仕事の型ができるでしょうか。
それは「あいさつ」です。
あいさつは、相手とのコミュニケーションのきっかけをつくる最初のアプローチであって、基本中の基本でしょう。
しかし、廃れていく会社は、この基本が出来ていないのです。
高野さんはこう言います。
あいさつは新入社員がするもので、上司はあいさつをされるものだと思っている組織がとても多いのです。(中略)あいさつをすると先輩が、まるで「あいさつを返すのは面倒だからしないでくれ」とでも言いたげな顔をする。すると初めは元気にあいさつをしていた新入社員もだんだんとしなくなる。そうやってあいさつのない会社がまた一つできあがっていきます。だから、その会社のあいさつとは何かを真剣に考えて、上の立場にいる人ほど先に気持ちのいいあいさつをすることが大切なのです。
ふんぞり返っている上層部、初心を忘れた職場の先輩には、耳の痛い話でしょう。
あなたやあなたの会社は、コミュニケーションの基本であるあいさつがきちんとできているか。
まさに氏の言う「上の立場にいる人ほど先に気持ちのいいあいさつをすることが大切」なのだということを肝に銘じたいところですよね。
仕事の型の展開法
さて、これら仕事の型の基本が身についたとしたら、その先はどのような展開が望まれるのでしょうか。
それは、臨機応変に対応できる能力を身につけられるかどうかです。
具体的な逸話として、ある地方のコーヒーショップでおもらしをしてしまったお年寄りの話がありました。
それに気づいた若いウエイトレスがお茶をわざと膝にこぼしたというのです。
そして「申し訳ありません。手がすべってしまいました」「大浴場に着替えを用意いたしますので、そちらまでご一緒願えますでしょうか」と言ったそうです。
すごいですよね。
なぜ、このような臨機応変な仕事ができたのでしょうか。
高野氏は、このウエイトレスにはセンターピンである「絶対にお客様に恥をかかせないこと」が見えたからこそ、できたのだと解釈しています。
センターピンを見抜く。これは感性を磨き続けていないと、なかなかできるものではありません。しかし、自分のアンテナを高くして、あらゆる可能性を意識して働けば、年齢に関係なく見えてくるものです。
お客様にとってのセンターピンは何かを考えながら働く。
たしかにこれは、サービス業における仕事の型の応用であり、また、それ以外の業種でも使える考え方ではないでしょうか。
「お客様にとっての」の部分を「取引先にとっての」とか「同僚にとっての」と言い換えれば、まさにあらゆる角度から応用可能な仕事の型となるでしょう。
我々はとかくマニュアルに縛られ、そこから仕事を発展させることができていないように思えます。
マニュアルの存在に囚われ、目の前の顧客のセンターピンを見ようともしない。
高野さんもこう言います。
マニュアルという言葉が日本に入ってきて、それが一般的になって、日本に古くからある型という言葉と入れ替わってしまったことで、私はサービスの一つ一つの形に込められていた本来の心が見失われてしまったように思えてなりません。型がもっている心のあり方、その大切さというものをどこかに置き忘れてしまったのではないでしょうか。
仕事の型の展開法、すなわち「センターピンを見抜く力」を養えるかどうか。
仕事の型を身につけた人とそうでない人との間には、仕事に対する意識の差、それ以上の圧倒的な仕事ができる(シゴデキ)職業能力の差が生まれてしまうように思えてなりません。
これは、サービス業以外の技術職や管理職と呼ばれる人々にも当てはまるはずです。
仕事の型となる基本を身につけ、そしてセンターピンを見抜ける応用も身につける。
これでこそ、エキスパートと言えるのでしょうし、また、それができる者とできない者との差はあまりにも露骨に致命的な格差として、周囲にも自分自身にも響いてくることでしょう。
私たち自身が仕事の型を意識して、プロとしての振る舞いが出来ているかどうか、再点検が必要だと思わされました。
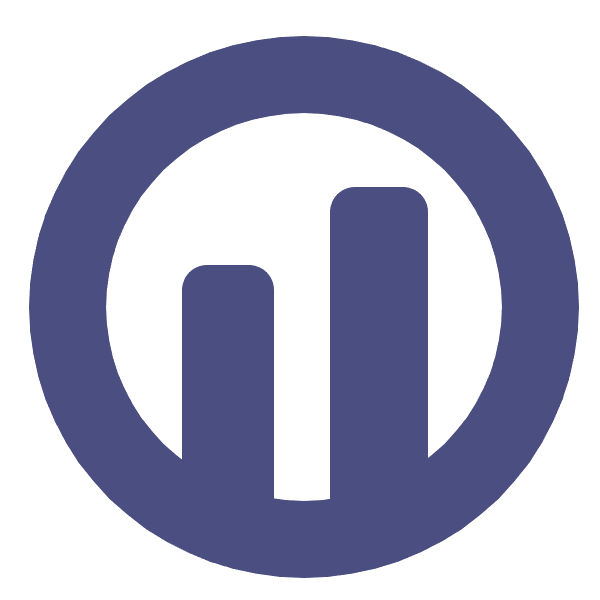 THE BUSINESS TIMES
THE BUSINESS TIMES