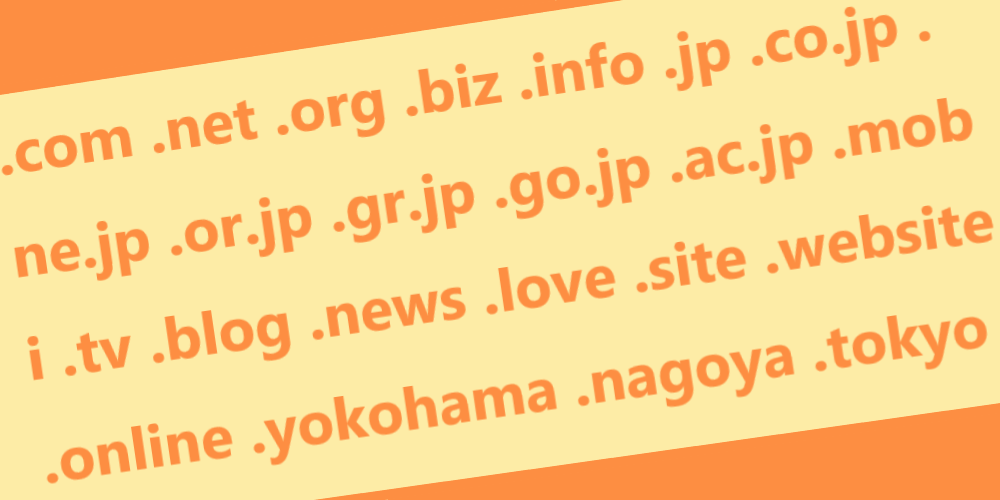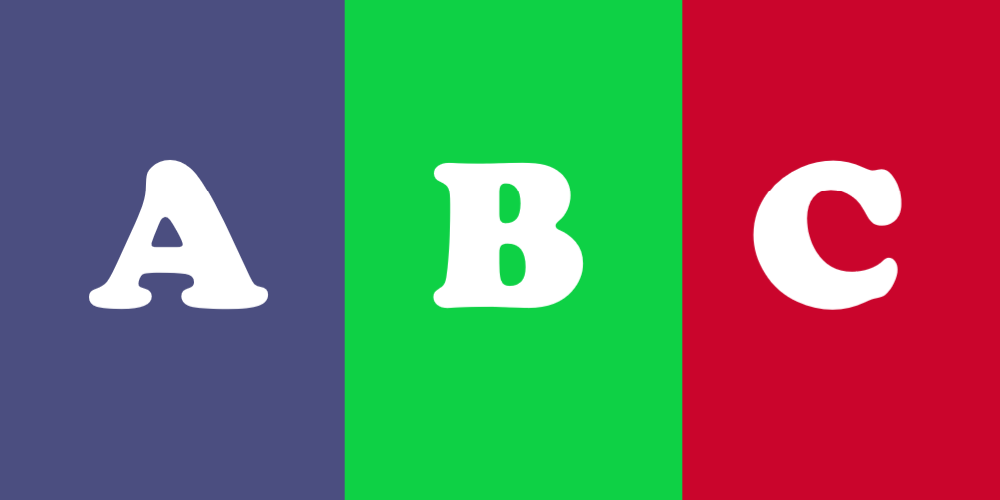みなさんは、高野登さんという方をご存じでしょうか?
ザ・リッツ・カールトン大阪の開業時に尽力された方で、経歴もアメリカでの修行などを通じて「本当のホスピタリティとは何か」を探求されたホテルマンだと認識しています。
そんな私は利用者側であって、サービスの提供側ではありませんが、高野登さんの著書を好んで拝読しています。
たしかに著書の多くは、ホテルなどでサービスを提供される方に向けて書かれた書籍タイトルとなっています。
しかしこれが、宿泊客だったとしても一読の価値があるのです。
それは単に私がホテル好きだからということではなく、会社員だろうが、経営者だろうが、専業主婦だろうが知っておきたい「人としてのあり方」について知れるからです。
高野さんはホテルマンですから、ホテルのエピソードが多くなってしまうのはやむを得ません。
問題はそこではなく、彼の中心的価値感と思われる「人としてのあり方」について触れることが大切なのです。
どうやったら人を喜ばせることができるのか
どうやったら人を喜ばせることができるのか?
この視点は、ビジネスパーソンにおけるビジネスシーンのみならず、家庭や恋人同士でも使える考え方のはずです。
高野さんは、自身の経験を通じて、このホスピタリティの体現をどうすればできるのか、具体例を交えてお話ししてくださっているのです。
思い返してみれば、例えばビジネスパーソンが対顧客、対同僚、対取引先、対家庭、対友人、対社会に対して、ホスピタリティ溢れる接遇が出来ているでしょうか。
- 「お客さんはともかく、同僚には厳しく当たっているかもしれないなぁ」
- 「下請け先に対して、横柄な態度をとっているかもしれないなぁ」
- 「街中で困っている人がいたとしても、見て見ぬふりをしているなぁ」
こういった思い当たる節はないでしょうか。
同じ職場で働く仲間をリスペクトする、部下の従業員満足度を上げる、こういった感覚を持っている人は少ないと思われます。
おもてなしの心は、お客さんにだけ向ければよいのではありません。
自分自身がホスピタリティの塊となり、いかなる人に対しても自然と気づかいができるようになる。
これが、高野さんの提唱されたい世界観ではないでしょうか。
だとしたら、大変共感するところです。
仮にこんな経営者がいたら嫌でしょう?
- 「従業員は低額使い放題。こき使ってポイ捨てすればいいんだ!」
- 「低賃金で過酷な仕事で文句あるか?代わりはいくらでもいる!」
- 「お客さんの前ではニコニコするよ。でもバックヤードでは怒鳴り散らすに決まってるだろ!」
- 「お前ら従業員の休憩スペースはボロい家具の配置で十分。お客さんは別だけどな!」
- 「客が嫌がっていても契約取ってこい。クレームが来る?そんなのお前が処理しろ」
こんな自分勝手な理屈で経営されてしまったら、周りの人は嫌な気持ちになってしまいますよね。
それが意欲の低下、パフォーマンスの低下、連携ミスの多発、優秀な人材ほど早期退職するなど、何も良いことは起きません。
「自分さえよければそれでいい」の対極にあるのが、人を喜ばせようとする「ホスピタリティ精神」です。
ですから、高野さんの本もそうですが、ホスピタリティをどう発揮するかという類の本は、どれも心温まることが多いように思います。
おもてなしの心で接しなくてもいい人なんていないのですよ。
日々の生活の中でそれを意識して、普段からおもてなし精神を発揮できるような人になることが人としてのありようではないのでしょうか。
忙しい日常で忘れがちですが、そういった人でありたいと思う今日この頃です。
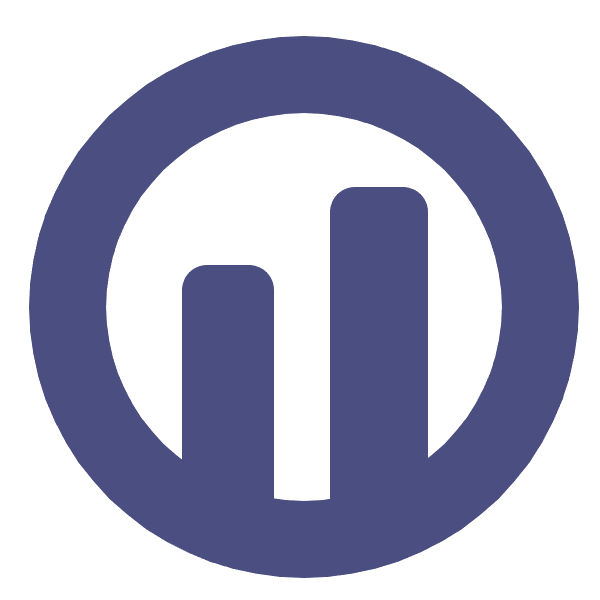 THE BUSINESS TIMES
THE BUSINESS TIMES